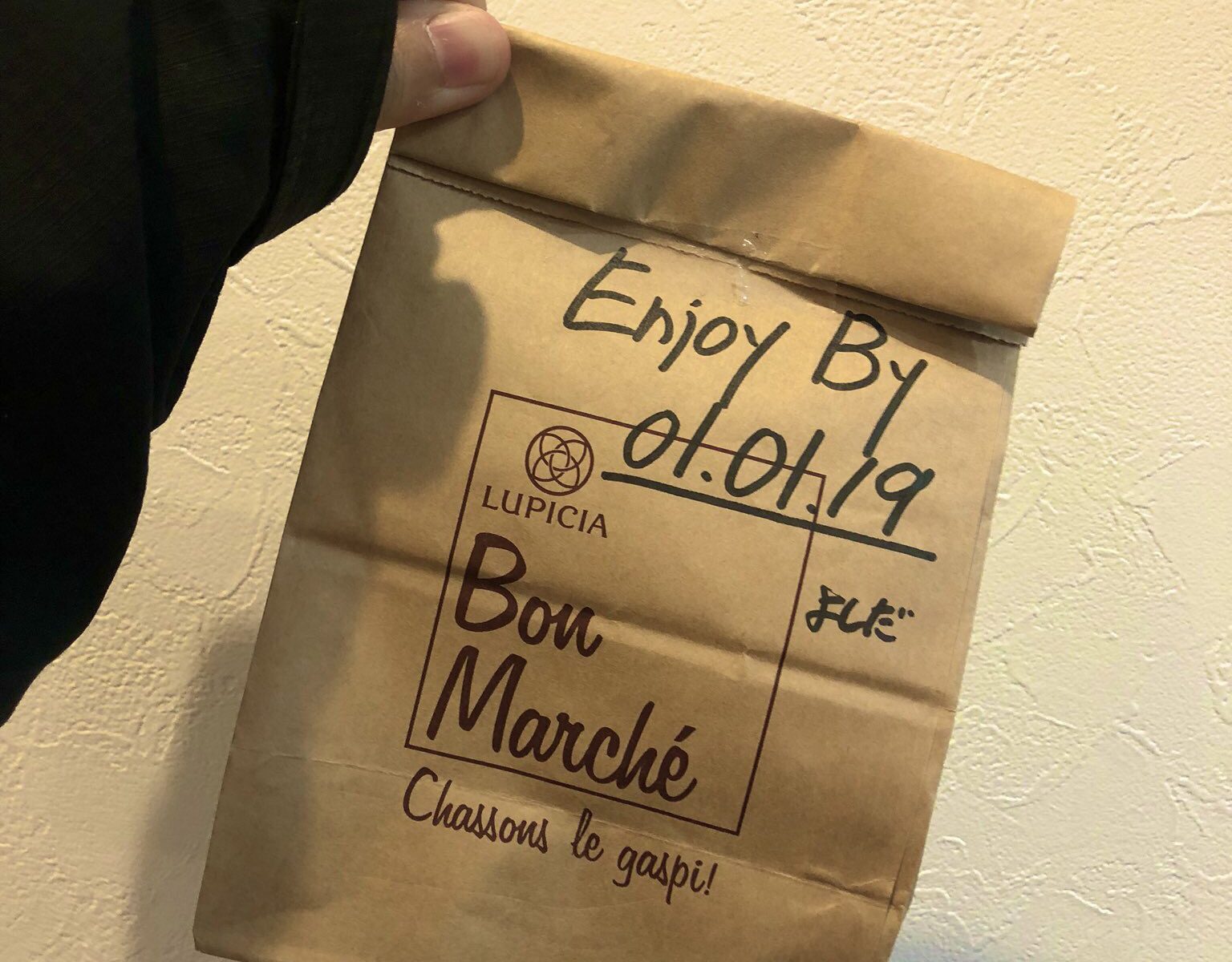こんにちは、よしだじゅんやです。
以前綾部と対談したものの原稿があがってきました。僕が酒をのみながら気持ちよく話をし続けたので、ずいぶん編集者泣かせだなあなどと他人事のように静観していたのです。が、あやべの編集をみてすごい感動した。ざっくばらんに語れた話を、話の流れを腰おらない程度にクッションいれたり、超約したり、大胆に切り捨てることで、しつかりと芯が通った記事になっていた。これは僕も頑張らないとなと背筋が伸びる思いがした。
ぜんぜん話が変わるが、僕は相棒がほしい。どうしても相棒がほしい。僕よりも速度感があって、そして、僕に新しい世界を提示し接点を生み出してくれるひと。速度感はまあ、目を瞑ることはできるが、どうも新しさを常に与えてくれる人はなかなかいない。会うたびに思考が飛躍しアイデアが生まれ、次の瞬間には手を動かしている。そんな相棒が棒はほしい。
一年前まで、僕はそのような相棒がいたような気がする。別に仲がよかったわけではないし、むしろ悪かったのかもしれないが、お互いに本というものを中心にサブカルチャーの知識が十分あり、常に更新されるカルチャーを追い続けていたので、会うたびに傾向を確認しあい、その流れのなかで自分はなにができるのかということをいつも語りあっていた。つまり、お互いの興味の方向性がにていた上に、手を動かす速度が速かったので、相乗的に歩むことができたのだろう。
「俺さ、雑誌作りたいんだよ」
「あ、俺もそろそろ作ろうと思ってた」
という会話が成り立ち、そのまま朝の5時まで営業している中華料理屋に入ってビールをのみつつすぐにコンセプトとコンテンツを組み立てていった。
「俺らを形作った多様なカルチャーを、つながりを意識しながら、網羅的に乱雑に提示するだけの本をつくろう。極力僕たちの説明を含めずに、ただカルチャーだけを提示し続けるってやつ。」
「いいねえ」
「もうさ、いきなりゴッホの自画像をどかんと提示しよう。次のページはキースへリングのアートワークを見開きに提示してさ、つぎのページは村上春樹の「ねじまき鳥クロニクル」の冒頭の一節がのってるんだよ。余白たっぷりにさ。どう最高じゃない?」
「いいねえ。おれさlineのスクショをただただ張り付けるだけのページ作りたい」
「いいじゃん」
「とにかく、好きなものをただ貼り付けよう。そして流れとレイアウトの作りこみでオリジナリティをだそう。著作権の問題は怒られてから考えようよ笑」
「オッケー、俺らが頼んだら置いてくれる店10店くらいあるし声かけていくか」
で、ゴリゴリ作っていった。アポも取り、製本もした。これをものすごい速度感で回していった。あの本を一緒に作った彼との関係性は、友達でも、親友でも、ライバルでもなく、相棒だった。
相棒、ほしい。とんでもない力で俺をどこかに連れていってほしい。楽しかったら俺は喜んでついていくし、必死に手をつかい頭をまわすはずだ。俺に未知の世界を見せてほしい、そしたら俺はお前に未知のものを与えることもできるはずだ。来い、相棒よ。
今日も読んでくれてありがとう。ぼくのダーリンは「よしだの相棒」採用もしています。うーん、アイデアの喧嘩がしたいのかも。