「わたしね、文がどうしようもないほど愛おしいの」心に治る見込みもないほど大きな傷を背負った妙齢の女性は小学生になったばかりのわたしにそう告げた。
北の国の奥の奥、わたしが生まれた何もない街に昭和の匂いがまだ残るおばあちゃんの家がある。その隣にある小さな家にわたしは遊びに来ていた。妙齢の女性は微笑んで迎えてくれた。彼女はわたしの父のいとこで、ずっとこの街に住んでいる。時折お邪魔しては遊んでもらっている。彼女は結婚していて旦那が仕事でいない昼にお邪魔することが多かった。
わたしは彼女が親戚の中で一番好きだった。耳を失ったわたしを寄り添い、手話を一生懸命覚えて様々な話をしてくれた。本当は毎回会いたいけど時折でしか会えないのは大きな傷を背負った心が悲鳴をあげ、一日寝込んでしまう時が多いからだった。遊びに行く日の朝に必ず体調の確認をしては良い時にお邪魔をしていた。
「君もたくさん、文を読むといいよ」
彼女に読書を勧められたからわたしの小学時代は本の虫だった。学校の図書館、街の図書館によく訪れてはたくさんの本を借りてずっと読んでいた。彼女の言う通り文はとても素晴らしいものだと小学低学年にして知ったのだ。
ある日、彼女の家にお邪魔していたときだった。彼女はいくつかの文章が書かれた紙をわたしにくれた。そこに書いてあるのは歌詞だった。
「わたしが好きな音楽なの。音楽は聞くことが難しくても読むことはできるわ。わたしが好きな音楽の歌詞を書いてみたの」
音楽が好きな彼女は「心を掴む言葉がたくさん、音楽にはある」と言った。何枚か並べられた紙の中でわたしが今も覚えているフレーズがある。
あなたの時代が終わったわけでなく
あなたが僕らと歩こうとしないだけ
作詞が小田和正の「僕等の時代」だった。
「この言葉は今のわたしに強く叱られているような気がして、これを聞くたびに今のままではダメなんだっていつも思っちゃうよね」
その言葉をその時は意味がよくわかっていなかったが、今ならわかる。彼女は想像を絶する過去を抱えていてそれが原因で心に深すぎる傷を背負ったのだ。だからこそ「僕等の時代」は彼女の心に深く深く突き刺さっていたのだ。
その頃ちょうど国語で詩の勉強があり島崎藤村の「初恋」をやった。「人こひ初めしはじめなり」というフレーズに突き刺さり、さまざまな詩集を読み始めた。当時に古文もハマっていった。古文は松尾芭蕉の「おくのほそ道」の最初にある「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。」がきっかけだった。
そしてわたしの中でとある感情が芽生える。人の心に響くような、詩を、歌詞を、書いてみたい。その頃からわたしは書き始めたんだ。初めて書いた作品を初めて見せた相手は彼女だった。
「君は素敵な文が書けるんだね」
彼女の出会いがなければ文芸創作をするわたしはなかったかもしれない。彼女が人生で大きなキーパーソンのひとつだったかもしれない、とわたしは思っている。
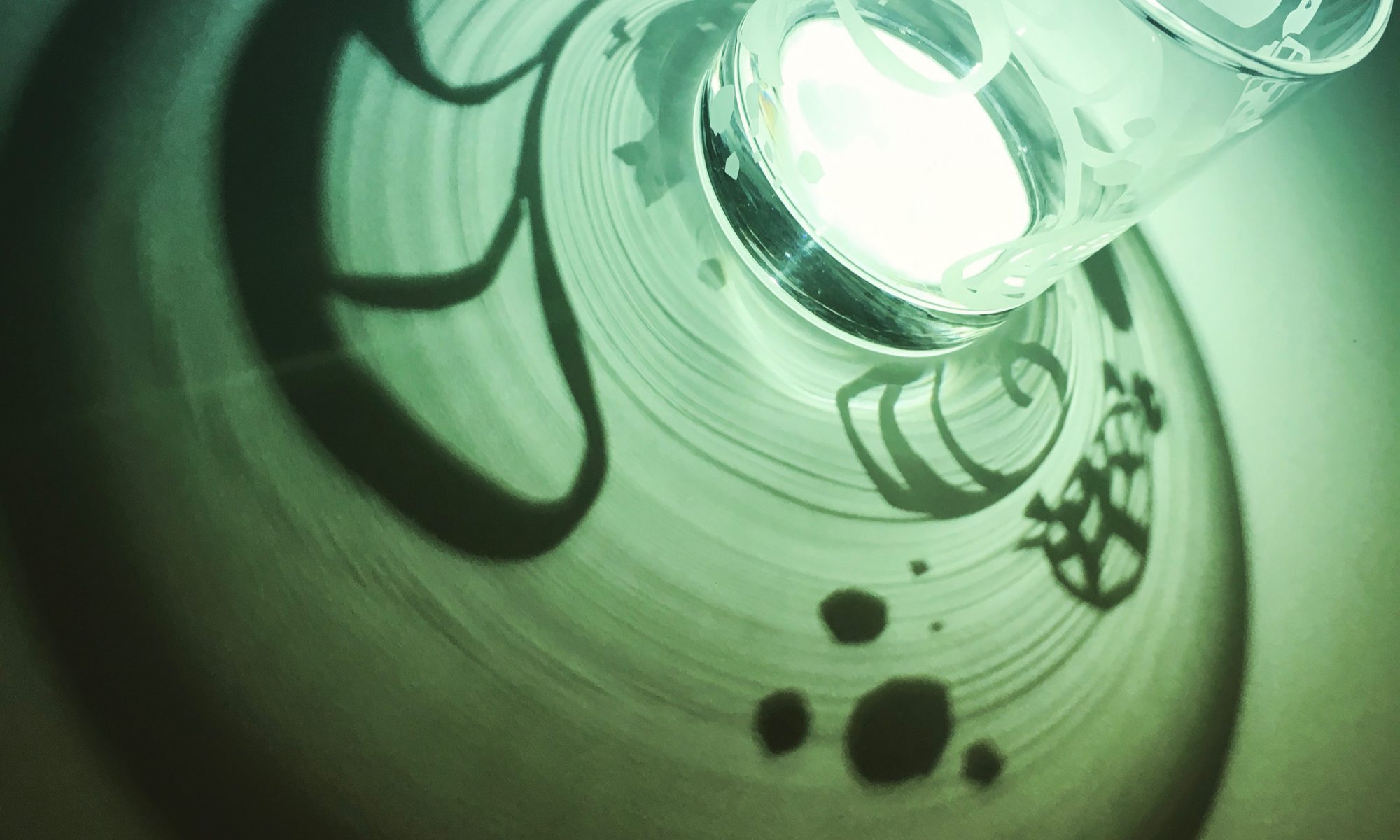
私が文章を愛するようになったきっかけはあさのあつこ「バッテリー」がきっかけでした。
日本語には奥深いものがあると思います。
さとりの文章好きです。
今後も楽しみにしてます。
あさのあつこの「バッテリー」わたしも読みました。全巻読みました。いい青春を描いてて惹き込まれますよね。
ありがとうございます、嬉しいです。