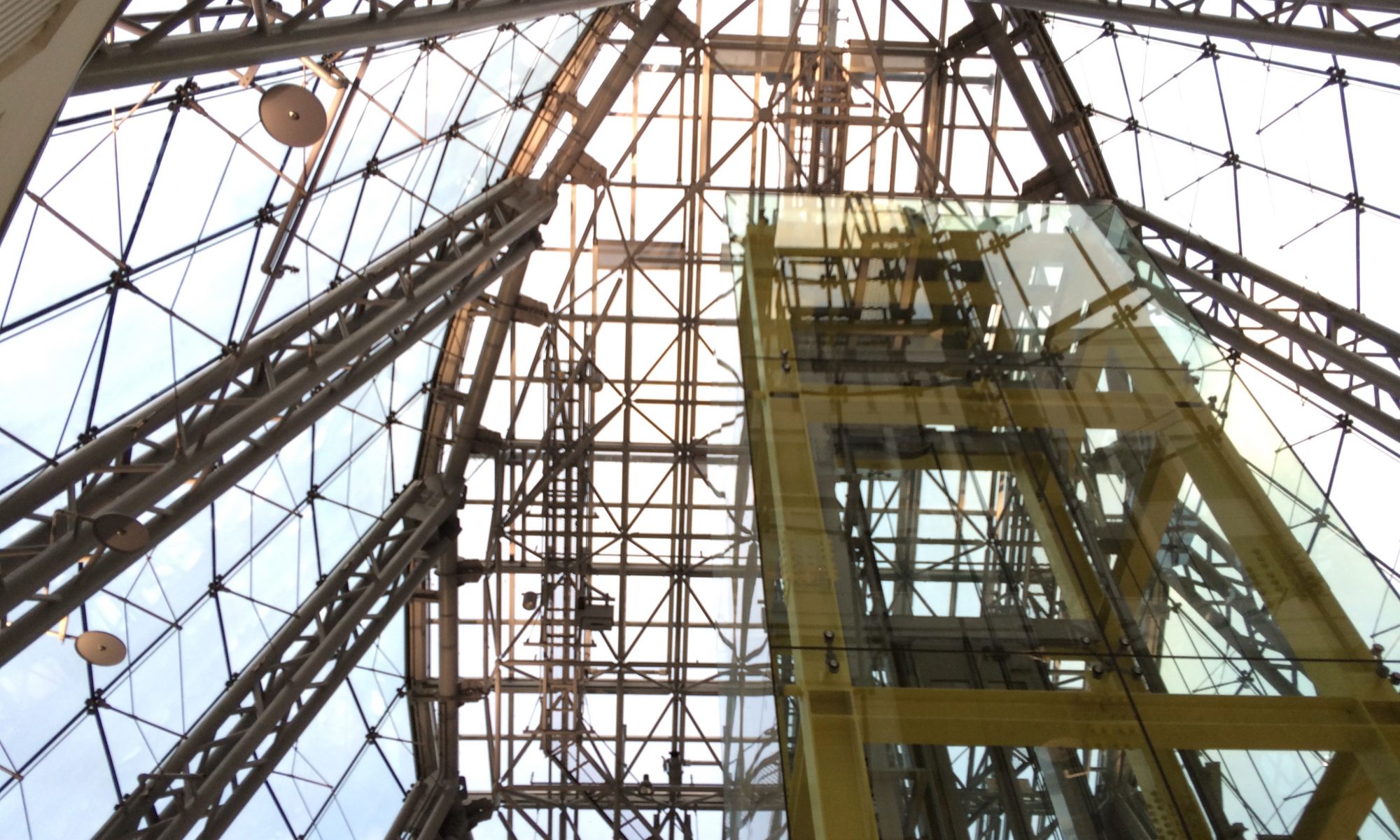「つまりだ、俺の声はどうやっても君の耳に入らないってことね?」男は少し悲しそうな表情を浮かべた。
耳の機能を備え忘れたまま生まれてしまったわたしが耳の機能を備え持つ人々と会話をする時は目を酷使するのだ。
相手の口の形を読み取って脳内で会話の流れの文章を作り上げて様々な情報を数多の本棚から引き出してパズルのように当てはめている。口の形だけではなく相手の表情だったり身振りだったり視線だったりと些細なところまでしっかり見てそれらを付加情報として脳内アップデートをする。会話の流れをしっかりつかんでその先を予測、その上で自分はどんなことを言いたいのかまでを同時に脳内処理を行うのだ。
はっきり言って耳の機能を備え持つ人々と会話をするのは楽ではないのだ。脳をフル稼働しなければならない重作業なのだ。
わたしが主に使う言語は手話であり、同じ耳の機能を備え忘れて生まれた友人との会話は手話を使っている。わたしにとって一番楽な会話は手話だ。相手の細かい動作まで察知し会話をパズルのようにはめる必要もないし、会話の流れを予測する必要もないし、精度の低い脳内処理でも十分対応できる。
耳の機能を備え忘れて生まれてしまった人々は個人差がある。耳の機能を20%ほど欠如している人もいれば、機能そのもの備え付けられていなくて外枠として耳を取り付けただけの人もいる。わたしは後者の方だった。耳はもはやアクセサリーとでしか役割を果たしていない。
補聴器、とかいう音を大きくする現代の技術の結晶がある。それはありとあらゆる音をありえないほどの大きさにして耳に届けることができる。音を大きくする耳の機能を備え忘れた人にとってはその結晶を装着するだけで聞き取れることもあるようだ。
しかしわたしは耳の機能そのものを備え付けられていないため、大きくした音を感じ取ることはできれど、その音の正体を見破る機能がない。ただただ音を感じ取って終わるのだ。
という話を耳の機能を完璧な程まで備え付けられた男性に話したのだ。
「つまりだ、俺の声はどうやっても君の耳に入らないってことね?」彼は少し悲しそうな表情を浮かべた。
「まあそうなっちゃうね、そうだね」否定しようがなかった。「でも、口の形だったり身振りだったりで君の言いたいことは伝わるよ」
「そうだよね、大事なのは心だな、ソウルトークだな!」
ソウルトーク‥に不覚にもわたしは笑ってしまった。耳の機能を備え忘れた人を欠陥人として差別し遠さがるようなことを彼はしないのだ。
確かに耳の機能を備えつけられた人々と会話をするのは疲れてしまうけど、それは相手も同じなのだろう。
声だけで今まで通じたのにある日突然、声だけでは通用出来ないようなわたしのような人間に出会ってしまったのだ。それでも逃げず差別せず遠ざけず向き合ってくれる人々を、わたしも大切にしたい。
ソウルトークで乗り越えよう。